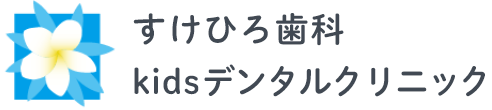-
2023.09.09
子どもの歯並び~機能訓練~
上顎が拡がった後、歯と歯の間の隙間ができたらいよいよ歯並びの改善に入りたいところです。
しかし、歯並びが悪い原因を突き詰めていくと、鼻呼吸が上手ではないことが顎や歯並びの成長を阻害している根本の原因なので、この鼻呼吸の改善をしなければなりません。
そのためには、お口ポカンの改善、つまり口唇閉鎖不全の改善させお口が閉じるようにする、飲み込みが下手っぴな場合には舌の使い方の訓練をして、舌の先が上顎につくように持っていくなどの改善が必要になります。
すぐに準備できるものとして、ガムや風船、吹き戻しを用いて訓練する方法などがあります。
お口がしっかり閉じきれない子は風船を膨らませれなかったり、吹き戻しができなかったりします。
歯科医院では、この口唇圧を検査する器具があり数値化することにより現状がどのくらいのレベルで、訓練によりどう改善したかを評価することができます。
なぜ、このような機能の評価が必要になるかというと歯は外からは口唇圧、内からは舌圧を受けてバランスの取れたところに並ぶからです。
口唇圧・舌圧の片方が強く、片方が弱くという状態になると歯は本来の場所からずれてしまいます。なのでしっかりとした口腔機能の獲得が必要なのです。
-
2023.09.06
子どもの歯並び~上顎を拡げる③~
拡大装置によって上顎が拡がると、上顎の中央部分、いわゆる硬口蓋と呼ばれる部分が下方にきます。
これは、上顎が横に拡がることで、口蓋にも横に拡がる力がかかり結果下方に移動するのです。
上顎が横に拡がる、つまり幅が拡がることで様々な変化が起こります。
・鼻腔も拡がり鼻呼吸がしやすくなる
・舌が上顎にペタッとつくようになり飲み込みやすくなる
・お口ポカンが改善しやすくなる
・歯と歯の間の隙間ができて歯が並びやすくなる
・上顎の拡大によって下顎の拡大がしやすくなる
つまり、
上顎が拡がる→鼻呼吸の獲得→適切な上顎の成長の獲得→叢生(歯のガタガタ)リスクの改善・歯並び改善の下準備
という流れになるのです。歯並びの改善には、鼻呼吸という「機能」の改善が必要なのです。
-
2023.09.05
子どもの歯並び~上顎を拡げる②~
今回は上顎を拡げるのに用いる装置についてです。
顎を拡げるための装置を拡大装置といい、上顎用、下顎用があります。そして、どちらも取り外しが可能な床拡大装置、固定式のスケルトンの2つに大別されます。
取り外し式、固定式それぞれにメリットデメリットがあります。
まずは、取り外し式についてです。
<メリット>
・取り外しが可能なのでお口の中を清潔に保ちやすい
・違和感なく食事ができる
・ネジが回しやすい
<デメリット>
・正しくつけないと効果が発揮されない
・管理が悪いと破損してしまう
続いて固定式の装置についてです。
<メリット>
・顎が拡がりやすい
・取り外し式に比較し破損のリスクが少ない
・適応症が広い
<デメリット>
・歯みがきがしにくくなる
・慣れるまで、取り外し式に比較してネジを回しにくい
どちらの装置も長所・短所があります。お口の中の状態、お子様の性格などを考慮して使用する装置を決めるのが重要です。
-
2023.08.31
子どもの歯並び~上顎を拡げる①~
前回は、狭い上顎は拡げて口呼吸を改善しましょうというお話をしました。
今回は実際にどのようにして上顎を拡げるのかをお話します。
上顎は上顎骨と呼ばれる骨で構成されています。この上顎骨は左右別々の骨が中央で結合しています。この結合部分は骨を作る細胞が活発で横に拡げる力をかけると更に骨を作る働きが活発になります。
この骨を作る働きを利用して上顎を拡げていくのです。
方法としては歯根がしっかりしている奥歯に装置をひっかけて、装置中央にあるネジを回すことで上顎を横に拡げる力が発揮されます。
この装置を拡大装置と呼びます。拡大装置には取り外し式、固定式の2種類があります。
拡大装置は上下それぞれにありますが、まずは上顎から使用していきます。上顎はおよそ2~4か月程度かけて拡げていきます。
この装置による痛みは、我慢できる程度のものでこれまで使えなかったお子様はいません。
歯並びは歯をきれいに並べて終わりではなく、原因である機能的な部分を改善することがとても重要なのです。
-
2023.08.30
子どもの歯並び~口呼吸について②~
前回は、口呼吸の引き起こす様々な影響についてお話をしました。
今回は口呼吸に対する歯科的なアプローチについてです。
口呼吸をしている子の特徴として、上顎(口蓋)が深く、鼻腔の体積が狭くなっているということをお話ししました。
上顎が深い子は、上顎の横幅、特に前から3番目の左右乳犬歯間が狭くなっていることが多いのが特徴です。
この左右の乳犬歯間の幅が狭いと、前歯が4本並ぶスペースが不足して生えかわりの時期、つまり永久歯萌出に伴いガタガタが出てくることがあります。
また、上顎の成長発育が少ないと、下顎にも影響がでます。具体的には、下顎も成長がが不十分となり下顎前歯もガタガタになります。下顎前歯の方が先に生えかわりが起こるので、その時に歯並びを意識し始める方多いですが、実は口呼吸やいびきなど前歯のガタガタのサインは、早くに出てきます。
ではこの口呼吸の対策、何をしたら良いのかというと、鼻呼吸をしやすい機能作り、つまり上顎を拡げて鼻腔の改善を図ることです。
上顎を拡げると、幅にゆとりがでてくるので歯が並びやすくなります。そのようにすることで歯の重なりを解消していくのです。
-
2023.08.26
子どもの歯並び~口呼吸について①~
前回、いびきがある子は口呼吸があり、気道が狭くなっていますという話をしました。
では、口呼吸をしていると、いびき以外にどのようなことが起こるのかというと、
・鼻がよくつまる
・口がポカンとあいていることが多い
・猫背になっている
・食事が遅いまたは異常に早い
・食事中にペチャクチャ音を立てる
・中耳炎になりやすい
・目覚めが悪い
・風邪をよくひく
など影響は様々です。では、どのようなアプローチがあるのか?次回は歯科的観点からの対処法についてお話をします。
-
2023.08.24
子どもの歯並び~いびきについて②~
前回は、いびきと口呼吸の関係、いびきがある子は顎が小さくなるという話をしました。
口呼吸のある子は、上顎の中央(口蓋)が深く、その分鼻腔の体積が小さい傾向にあります。
さらに、鼻腔の左右を隔てる鼻中隔が湾曲してしまい鼻呼吸を難しくしてしまいます。
そのため、口呼吸をせざる得ない状況になってしまうのです。
口呼吸によってお口の中や喉の乾燥を引き起こし、更には扁桃腺の炎症を誘発します。
すると、空気の通り道である気道が狭くなるので、いびきが出るのです。
つまり、いびきは口呼吸をしているという重要なサインなのです!
-
2023.08.23
子どもの歯並び~いびきについて①~
お子様の歯並びについて、何回かにわたりお話ていきます。
タイトルにありますが、初回は「いびき」についてです。
一見、「えっ!?どうして歯並びの話なのにいびきなの?」と思われた方が多いと思います。じつは子どもの成長発育、特にお顔、顎の領域における成長では、いびきの有無が重要な項目の一つになっています。
いびきがある子の特徴は、就寝時に口呼吸をしていることです。そして口呼吸の原因は鼻の中の空気の通り道が狭いことに起因し、その通り道の幅は顎の大きさに関係しています。
つまり、いびきがある子は顎が小さいことが多いのです!
-
2021.08.23
乳歯のむし歯
乳歯のむし歯、「生えかわるから大丈夫」と思わないでくださいね!
乳歯にももちろん神経があるので、放置すると痛みの原因になります。
また、大きさとできた時期によっては、乳歯の下で育つ永久歯の
形成不全を起こしてしまうことがあるんです。
乳歯のむし歯がある口腔環境に新たに永久歯が生えてきたら
永久歯もむし歯になりやすくなってしまいます。
大切な永久歯を守るためにも治療を受け、
予防法を教わってむしばを食い止めましょう!!

-
2021.08.18
紹介プレゼント☆
当院にかかられている患者様はご存知の方が多いと思いますが、
当院では紹介特典のプレゼントのお渡しを行っております。
当院を紹介してくださった方、紹介でいらっしゃった方、
双方にケアグッズのプレゼントを行っております。
プレゼントでお渡ししているのはキッズ用、成人用の歯磨き粉になります。
ご家族、お友達、職場の方で歯医者さん選びで悩んでいる方いらっしゃいましたら
是非当院で診せてください^^
小児矯正
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2023年 (8)
-
2021年 (3)
-
2020年 (17)
-
2019年 (9)