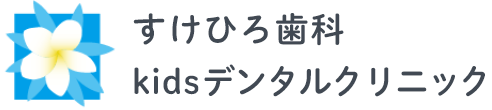-
2021.05.11
おこさまの歯並び
乳歯列が生えそろった状態で歯が横並びにぎゅうぎゅうに生えていると、
永久歯が生えそろったときに歯が重なって生えたり、違う所から生えてきたりと
歯並びが悪くなる可能性があります。
歯並びが悪くなる原因は決して遺伝ではなく、口呼吸や姿勢、
頬杖をついたりなど、普段からの癖が原因で起こってしまいます。
歯並びが悪くなると見た目だけでなく、
むし歯や歯周病のリスクまで高くなります。
もし矯正をお考えの方は、小学生になったくらいの6~7歳頃に
矯正治療を始める方が、骨が柔らかいため治療期間が短く済みます。

-
2020.09.26
「食べる」機能を診る~④お口ポカンの癖がある~
歯や顎は、くちびる、舌、頬の筋肉から受ける力によって馬蹄形にバランスよく成長していきます。まだ骨格が柔軟な小学校低学年までの間に、お口の周りの筋肉を鍛えることで顎の成長と歯並びにいい影響が出ます。
かみ合わせや、歯並びが乱れることで咀嚼がスムーズにいかずに食事がしにくくなることがあります。お口ポカンを見つけたら早めにお口を閉じる習慣を身に付けましょう!

-
2020.09.25
「食べる」機能を診る~③舌が動きにくい~
赤ちゃんの間は、体重の増加に問題がなければ舌の動きが悪くても舌小帯に対して特別な処置をする必要はありません。
但し、学齢期が近くなっても、活舌や食事に影響が出ている場合には、からだの成長や学校生活にも影響が出てくるので、一度相談されることをおすすめします。
舌の動きが改善されることで、活舌がよくなったり、奥歯に食塊を乗せられるようになり食事がとりやすくなります。
前方に舌が出にくい、左右に動かしにくい、前に出したときに引っ張られてハート形になるといった場合は舌小帯が原因かもしれません。
-
2020.09.19
「食べる」機能を診る
乳歯が生えそろう3歳頃から、食べる機能の発達の他、歯並びやかみ合わせも「食べること」に影響してきます。
- 前歯がかみ合わない
- むし歯が多い
- 舌小帯が短い、舌が動きにくい
- お口がポカンと開いている
このような問題があると「食べること」が苦手になりやすいので注意が必要です。
①前歯がかみ合わない
指しゃぶりがなかなかやめられない。このような状態が続くと顎の発達や前歯の傾きに影響を与え前歯がかみ合わない、いわゆる開咬という状態になります。
指しゃぶりは生後2か月ぐらいから始まり、授乳期、離乳期後期には手や口の発達に重要な役割を果たします。但し、それが長引いて4歳を過ぎても続くと、顎の成長・歯並びに影響が出てくるため、3才後半になったらやめるように積極的に促すようにしましょう。
自発的にやめることが重要なので、必ず言い聞かせることから始めることが大切です。
次回は②むし歯と食べる機能についてお話していきます。
-
2020.08.22
鼻呼吸から始める歯並び予防

お子様のお口が「ポカン」とあいていることはありませんか?お口で呼吸をしていると適度な口唇の緊張が失われてしまうこと、鼻腔が拡がらず上顎に適度な力がかからないなどの弊害が出てきます。
そうなると、歯並びや顎の成長に様々な影響を与えてしまいます。
具体的には、顎の成長量が不足して、歯並びが狭くなり窮屈になってしまうことです。
鼻づまりがある場合には、そこから改善することで将来の歯並び予防につながります。
言葉が分かるようになる3才頃からは、お子様のお口「ポカン」を見つけたら親子で改善に向けてアプローチすることが大切ですね。
-
2020.07.21
受け口の治療
受け口のことを専門的には反対咬合と呼びます。反対咬合には①「下顎の位置的なずれによるもの」、②「歯の位置のずれによるもの」、③「下顎骨の過成長もしくは上顎の劣成長によるもの」のいずれかが原因です。
①の場合は、下顎を正しい位置に誘導するための装置を用いて、下顎を後方に動かしていきます。治療は言葉が分かり指示が通る年齢・月齢である3歳頃から行うことができます。
②の場合には、矯正装置を用いて歯を正しい位置に戻し、噛み合わせの改善を図ります。多くの場合は被蓋関係といい、歯の重なりに問題があるケースがほとんどなので、歯並び全体の治療を通じて改善を図ります。
③の場合は成長発育の段階によってアプローチが異なります。成長期をまだ迎えていない場合には、成長の少ない上顎骨の成長を補助するためのトレーニングを行い上下ともに顎骨の位置関係が正しくなるように誘導していきます。
反対に、成長期が過ぎている場合には、全体の改善をするためには外科的に位置の修正を行わなければなりません。
受け口は多くの場合、幼少期の習癖から来ることが多いため、早めの治療が推奨されます。
-
2020.07.20
上の前歯が開いている!
6才頃から歯がだんだん生えかわってきます。上の前歯が生えかわると、歯と歯の間に隙間ができるいわゆる「すきっぱ」という状態になることがあります。もともと上の前歯は少し横に拡がるように生えてくるため、生えた直後に隙間ができることがあります。
出来た隙間は、前から3番目の犬歯という歯が生えてくるときに、少しずつ横に力をかけながら生えてくるため、時間経過とともに隙間が閉じてくることがあります。
それでも開きが大きいと戻りが弱いときがあります。それは上唇小帯と呼ばれる上唇から伸びているヒダに引っ張られているためです。このヒダが伸びすぎていると前歯が閉じるのを邪魔することがあります。
そのため、生えかわった際に、この上唇小帯が伸びている場合にはその位置を修正するための処置が必要になることがあります。
処置は麻酔後レーザーを用いて行うため、30分ほどで終わり、処置後の出血もほとんどありません。
必ず必要な処置ではありませんが、歯並び予防のためには大切な処置になります。気になる方はご相談ください。
-
2020.07.18
歯と顎の成長発育
歯がある程度生えてくると、隙間が無かったり、反対に隙間が大きかったり、歯が内側に入り込んでいたり、歯並び大丈夫かな?っと心配になることがあると思います。
また、学校や園の検診時にかみ合わせにチェックが入り心配される方もいるかと思います。
歯は生後6か月ごろに下の前歯から生えはじめます。そして2歳半から3歳頃までに乳歯はすべて生えそろいかみ合わせが完成します。
この際に歯が並ぶ顎の成長発育が不十分だと歯並びが窮屈になってしまいます。小さなお子様の場合、鼻の通りが悪くなりやすく、そのためお口で呼吸をしていることもしばしばです。
お口がポカンと開いていることありませんか?
お口がポカンと開いていると、お口の周りの筋肉が正しく機能せずに、筋肉が付着している顎の骨に正しい力が伝わりません。そのためお口が開いている子、閉じている子で成長に差が出てきます。
何気ない癖ですが、お口、歯並びの成長には大きな影響を与えています。
もし、お口がポカンと開いているのを見つけたら、親子でお口が閉じるように取り組んでいくことも歯並び予防の第一歩になりますので実践してみてください(^▽^)/
-
2020.07.14
グラグラした乳歯、抜いたほうがいいの?
6才前後になると、一番奥から6才臼歯と呼ばれる歯が生えてきたり、舌の前歯がグラグラしてきて生えかわったりします。お口の中の第2次成長の始まりです。
通常、子どもの歯がグラグラしてくると大人の歯がその真下まできているので大人の歯が生えてくる場所はもうすでに決まっています。
そのため、グラグラした乳歯には歯並びに影響を与えるような力というのはありません。なので基本的には食事の際に噛むと痛いなどの症状があって支障がある場合には抜歯を行います。この場合、お子様自身の希望がなければ抜歯は必要ではなく自然に生えかわるのを待っても大丈夫です。
グラグラした乳歯で抜歯が必要な場合は、歯茎が炎症を起こし、化膿している場合です。レントゲンで検査後、歯の生えかわりが近い場合、化膿している範囲が広く保存が困難な場合には前後の歯やこれから生えてくる歯への影響を考えて抜歯が必要になることがあります。
つまり、病的な場合、矯正治療の都合でない限りは、自然な生えかわりを待っても大丈夫です。
歯の生え方含めて気になることがありましたら、ご相談ください。
-
2020.07.06
乳歯の大事な役割
乳歯がむし歯でも生えかわるからそのままでも・・・ではいけません。
乳歯は大人の歯(永久歯)に生えかわりますが、乳歯には乳歯にしかない大切な役割があります。
乳歯はおよそ生後6か月ごろから生え始め、3歳までに子どもの歯並びは完成します。この乳歯に求められる大きな役割の一つは、永久歯同様「噛む」こと。つまり食事をとるということです。
この時期のかみ合わせは非常に重要で、食事等を介し顔面の筋肉を正しく機能させることで顎顔面領域の正しい成長発育へと導きます。
顎顔面領域の成長発育が不十分だと、のちに生えてくる永久歯の歯並びにも影響を与えます。
また乳歯の生えている位置も非常に重要で、生えかわってくる永久歯の道しるべの役割を持っており、歯並びが窮屈だったりすると後から生えかわってくる永久歯の歯並びが乱れやすくなります。
また早期に乳歯を失ってしまうと、永久歯が生えてくるときにどの方向に進めばいいのか分からなくなってしまいます。
つまり乳歯をしっかり管理することで、健康な永久歯の歯並び・かみ合わせの獲得につながるのです。
一生のうちで乳歯のある期間は短いですが、非常に重要な役割があるため日ごろのケアが大切ですね。
小児矯正
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2023年 (8)
-
2021年 (3)
-
2020年 (17)
-
2019年 (9)