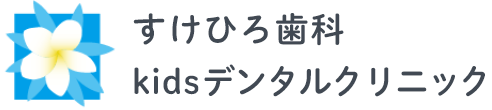2020.07.09
定期健診の間隔
むし歯予防、歯周病予防には定期的な検診・クリーニングが必要になります。個々人で歯並びやむし歯のなりやすさは異なります。
なので、定期健診の内容も期間も本来は個人で異なって当然です。
むし歯になりやすい人、歯周病が進行している人はもちろん、これらをしっかり予防したい方は最初月に1回程度で口腔ケアを行い、安定してきたら少しずつ期間をあけていくようにすることをおすすめします。
小さなお子様の場合は、まだ自分自身でしっかりとケアをしていくことが難しいこと、むし歯の治療をした個所はそうでない所に比較してむし歯になりやすいことを踏まえると、しっかりとケアができるようになるまでは間隔を詰めて管理していくことが必要です。
とくに4月、5月は外出することが少なかった方が多かったみたいで、家庭での間食習慣等が不規則になっている方を多く見かけました。
一度むし歯になりかけたりした場合には最初の予防行動が非常に大事になります。
最後の定期健診から期間が開いている方は早めの受診をおすすめします。
2020.07.06
乳歯の大事な役割
乳歯がむし歯でも生えかわるからそのままでも・・・ではいけません。
乳歯は大人の歯(永久歯)に生えかわりますが、乳歯には乳歯にしかない大切な役割があります。
乳歯はおよそ生後6か月ごろから生え始め、3歳までに子どもの歯並びは完成します。この乳歯に求められる大きな役割の一つは、永久歯同様「噛む」こと。つまり食事をとるということです。
この時期のかみ合わせは非常に重要で、食事等を介し顔面の筋肉を正しく機能させることで顎顔面領域の正しい成長発育へと導きます。
顎顔面領域の成長発育が不十分だと、のちに生えてくる永久歯の歯並びにも影響を与えます。
また乳歯の生えている位置も非常に重要で、生えかわってくる永久歯の道しるべの役割を持っており、歯並びが窮屈だったりすると後から生えかわってくる永久歯の歯並びが乱れやすくなります。
また早期に乳歯を失ってしまうと、永久歯が生えてくるときにどの方向に進めばいいのか分からなくなってしまいます。
つまり乳歯をしっかり管理することで、健康な永久歯の歯並び・かみ合わせの獲得につながるのです。
一生のうちで乳歯のある期間は短いですが、非常に重要な役割があるため日ごろのケアが大切ですね。
2020.07.01
歯科材料の強度
むし歯治療などで用いられる歯科材料には使える歯、部位などが決められています。各種材料で性質が異なります。
むし歯治療などでよく用いられる白い材料は、コンポジットレジン、通称CRと呼ばれています。色が白いので治療後目立ちにくいのが特徴です。材料の強度の点ではうすくなると割れやすい、時間経過とともに削れてくるという特徴があります。また時間経過とともに変色する可能性があります。
型採りが必要な場合によく用いられるのが、金属材料やセラミック材料です。
金属材料の特徴は強度で優れるという点です。なので余程のことがない限り破損することはありません。但し、硬さの点では歯に劣るため、時間経過とともに少しずつ削れてきたり、金属が伸びてきたりします。
セラミック材料は用いられるもので特徴が大きく異なります。
近年保険診療でも認められるようになったハイブリッドセラミックは、レジンと呼ばれる合成樹脂とセラミックと合成いわゆるハイブリッドです。金属を使用していないため、金属アレルギーの方にはお勧めの材料です。ただ、純粋なセラミック材料に比較すると、強度、変色といった点では劣るのが欠点です。
最近よく使用されているのがジルコニアと呼ばれる材料です。これは人工ダイヤとも呼ばれ、歯科材料の中では一番固いものになります。変色も少なくとても安定性の高い材料です。
せっかく入れた歯。壊れないに越したことはありませんが強い材料だけが一番優れているのでしょうか?
歯科で用いられる材料は、どの材料も硬さや曲げなどの強度の試験を経て認められたものだけが使用されています。
かぶせ物が壊れるということは、予測以上の力がかかっているということになります。一つは、使用部位の適正、もう一つは噛み癖など。
もし歯ぎしりや食いしばりなどの噛み癖があって、かぶせ物が壊れなかったら、場合によっては歯自体が折れてしまったりということにつながります。つまりかぶせ物が安全装置として働いているとも言えます。
それぞれの特徴をみてかぶせ物を決めることが非常に重要ですね。分からないことがありましたらご相談ください。
2020.06.30
歯を抜いたままにしておくと(+_+)
むし歯や歯周病、もしくは事故などで歯を失ったとき。抜けたままにしておくと様々な弊害が出てきます。
乳歯の場合、生えかわりよりも早く歯を失ってしまうと、次に生えてくる大人の歯が生えるための場所が失われてしまいます。なぜなら歯がないところの前後の歯が倒れこみ、隙間がなくなるからです。
そのため、早期に歯を失ってしまった場合には、歯が傾かないようにするための装置を入れることがあります。ただし、このような場合、歯並びが乱れる可能性が高いため、後々矯正治療が必要になることも多くあります。
大人の場合も、子どもと同じように、前後の歯が倒れこんだり、歯が伸びてきたりします。そうなると、かみ合わせが全体的に歪んできて顎や周囲の筋肉に負担がかかるようになり、痛みを伴う場合があります。これが顎関節症です。
歯並びやかみ合わせが大きく乱れてしまうと、歯を失った場所に歯を入れたくても入れることができなかったり、その後の治療が困難になります。
まずは、歯を失わないようにすること、万が一にも歯を失った場合には、早めの治療が必要になります。
2020.06.27
歯がしみるΣ(・□・;)知覚過敏?むし歯?
6月に入りだんだんと暑い日が増えてきました。暑くなってくると冷たい物を食べたり、飲んだりする機会が増えてくると思います。
そんな時に歯がしみたりすると・・・
なかなか冷たい物を楽しむことができませんね。
歯がしみる原因には、知覚過敏やむし歯などがあげられます。
歯はエナメル質という硬く、外から様々な刺激に対して耐久性を示す部分でおおわれています。
このエナメル質が破壊されたり、削れたりしてダメージを受けると歯はしみるようになってきます。
そのダメージの原因としてはむし歯や咬み癖(歯ぎしり・食いしばりなど)、歯ブラシの当て方、歯周病など様々でです。
時間が経てば落ち着く場合もありますが、なぜしみているのか?原因を特定し早期の対応をしておかないとさらに悪化してしまうことがあります。
夏を快適に乗り切るためにも、検診にて原因を解明して早めの対策を取りましょう!
2020.06.23
最近の検診の傾向
新型コロナ感染症がやや落ち着き、少しずつ日常が戻りつつあるかと思います。
外出自粛期間を経て、久しぶりに検診で来院される方も多く、お変わりなく元気な姿を見せて頂き嬉しく感じています。
その一方で、外出自粛期間においていつもと異なる家での生活のためか、検診にてむし歯があるお子様がややいつもより多く感じます。
原因は様々ですが、外出自粛期間中に家庭での食習慣特に間食習慣が多くなったり、生活リズムの変化などがあげられます。
むし歯は初期の状態ではあまり症状は見られません。ある程度進行した後に痛み・しみが出てきます。
特にもともとむし歯リスクの高い方は注意が必要です。
定期受診と適切なケアを行い、むし歯0を目指しましょう!
2020.06.20
学校歯科検診、幼稚園(保育園)歯科検診
新型コロナ感染症の影響でこれから歯科検診を実施する園や学校も多いと思います。
学校検診では、一度に多くの園児・学童の検診を実施するため、むし歯の有り・無しで若干の誤差が生まれます。
検診にてむし歯にチェックがあった場合はもちろん、なかった場合も歯科医院にて検診を行ったことがなければ検診を行うことを推奨します。
歯科医院では、目では見えない歯と歯の間の部分をレントゲンで確認したり、むし歯にならないための歯みがきの確認などを行うからです。
むし歯にならないこと、歯周病の予防をすることも大事ですが、それ以外にも噛み合わせ、歯並びも見ていくことがとても大事になります。
2020.06.02
1歳半検診はどうして大事?
1歳6か月という年齢・月齢というのは、早い子で乳歯が4番目まで生えている状態になります。
前から4番目の歯は第一乳臼歯と呼ばれる奥歯の一つで、乳歯列における噛み合わせのかみ合わせで重要な役割を果たします。
これまでの前歯だけという状態から奥歯が生えてきたことにより、食べれるものが増える一方で、むし歯のリスクも高くなります。
この時期にむし歯になりやすい箇所は、上の前歯と奥歯のかみ合わせの部分になります。離乳食開始から一定期間が経っているため、むし歯予防としてフッ素の使用開始が重要になります。
ハミガキの方法だけが予防ではなく、正しい生活習慣、食生活を身に付けることでむし歯や歯周病の予防、歯並びの予防に繋げることができます。
また、仕上げ磨きや、検診等を介して子どもは自分以外の他人からお口の周りや中を触られる機会が増えます。
この積み重ねで、少しずつ慣れていくことから予防歯科は始まります。
ここから定期健診デビューをしてみてはいかがでしょうか?(^▽^)/
2020.06.01
歯茎は大丈夫ですか?
「歯茎が下がっている人、40代で8割以上!」
加齢や歯みがきの手法など様々なことが原因で歯茎は下がります。30代から発現者は増加し、40代で80~90%、50代以上のほとんどの方で歯茎は下がっているという報告があります。
歯茎が下がったときの自覚症状として、歯がしみる、物が詰まるなどがあります。歯茎は一度下がると元に戻すのは大変困難なため、気づいた時からケアをしていくことが大切です。
「露出した歯の表面が危険です!」
歯茎が下がると、それまで歯茎に覆われていた歯の根元が露出してきます。この露出した部分は象牙質と呼ばれ、むし歯への抵抗性が弱いという性質があります。つまり、歯茎が下がるとむし歯のリスクが高くなるのです。
「歯の根元はむし歯のリスクが3倍!」
歯茎が下がった人はそうでない人に比べて、5年後のむし歯になるリスクが約3倍高いといわれています。
根元の虫歯を防ぐには、まずは歯茎が下がらないように予防する、歯茎が下がってしまっている場合にはフッ素による予防する。
予防はその人、その時の状態で手法が異なります。自分に合った予防を見つけることが大切です。
2020.05.20
定期受診の重要性
先日、熊日新聞に掲載された熊本県歯科医師会から案内です。
お口を健康に保つことが全身の健康につながり、様々な疾患の重症化を予防します。お口の中を清潔にすることは、食事をおいしくとれるということの他、お口の中の細菌数を減らし、肺炎等の全身疾患のリスク軽減につながります。
自動車の法廷点検・車検は事故が起こる前に検査・整備をしておくという意味合いがあり、お口の健康についても同じです。
何かしらの症状が出たときには、虫歯・歯周病がある程度進行した状態なので、治療に際し歯や歯茎への負担が大きくなるばかりか、治療期間もその分長くかかってきます。
これまでしっかり定期健診を受けられていた方も、これから定期健診を受けようとされている方も、安心して受診できる環境を整えています。
すてきな健康生活を始めてみませんか?

http://www.kuma8020.com/pdf/coronavirus-10.pdf
予防歯科
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
TAGタグ
ARCHIVE月別アーカイブ
2026年 (1)
2025年 (3)
2023年 (8)
2022年 (1)
2021年 (39)
2020年 (55)
2019年 (24)